山本 円郁Enyu Yamamoto
花人
花人、行者・山伏。池坊から花の道へ。その後、なげいれ、たてはなを学ぶ。現在流派なし、無所属。山岳信仰、哲学、アニミズムなど、さまざまな歴史と文化を参照しながら、日本古来の自然観に根ざした生の実践と継承に取り組む。
作品集に『Post-Mortem Portraits: 死してなお生き延びる花』『贄花』、論考に「生殖器崇拝としてのいけ花」(『いけ花文化研究』第8号、2021年)など。長野県在住。

私がやりたいことは、はるか昔、流派などが生まれる前、いけばなや花道という言葉も型もなかった頃、ただ人と神をつないでいた、「純粋なる心の花」です。
古代の祈りの文化のなかには、必ず「花」の姿がありました。古代の人々にとって花は、神仏の領域へアクセスするための、とっておきの神器だったのでしょう。
私はその純粋なる心の花の文化を「原初いけばな」と呼び、探求と実践を繰り返していこうと思います。

花人
花人、行者・山伏。池坊から花の道へ。その後、なげいれ、たてはなを学ぶ。現在流派なし、無所属。山岳信仰、哲学、アニミズムなど、さまざまな歴史と文化を参照しながら、日本古来の自然観に根ざした生の実践と継承に取り組む。
作品集に『Post-Mortem Portraits: 死してなお生き延びる花』『贄花』、論考に「生殖器崇拝としてのいけ花」(『いけ花文化研究』第8号、2021年)など。長野県在住。


「花綵の会(はなづなのかい)」は、2020年より始まった花の教室です。ただ花をいけるだけでなく、花をきっかけとして、神や仏、生や死、人間や自然、そして社会や世界について考えるための、座学と実践の教室です。
※現在、個別開催のプライベートレッスンのみ受け付けております。ご希望の方はお問い合わせフォームよりご相談ください。
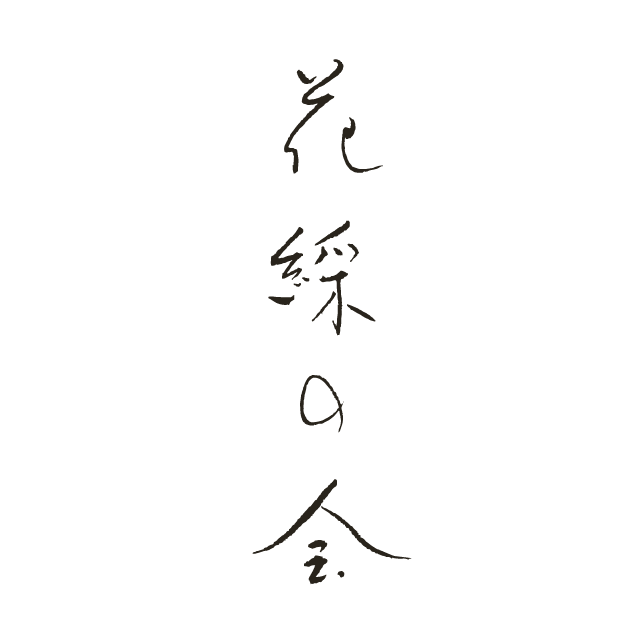
教室の名前である「花綵の会」は、イシス編集学校(故・松岡正剛氏創設)の寺田師範代より命名していただきました。ロゴの字は書家・箕浦敬子様に揮毫いただいたものです。
「花綵」とは、花の首飾りや色とりどりの綾模様を意味し、「つながり=縁」と響き合う言葉でもあります。また、日本列島は「花綵列島」とも呼ばれ、大陸にかかる花の首飾りにたとえられてきました。
四季のうつろいに抱かれた美しい日本、その日本で道を立てた花道。その文化の本質を忘れずに、そして何よりも“縁”を大切に、この会を続けてまいりたいと思っています。
祈りの花の実践にあたり、大切にしている考え方を以下の資料にまとめています。ぜひご一読ください。
花は、いける人の心を映す鏡です。良い花をいけたければ、自らの心を磨くほかありません。
催事・店舗でのいけこみ、出張教室・ワークショップ、執筆・講演のご依頼等、お仕事のご相談はこちらからお願いいたします。
状況や予算に応じて柔軟に対応いたしますので、お気軽にご相談ください。